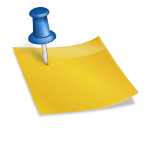「高く売れる会社」に共通する法務・財務の整備術
― スタートアップ・後継者不在企業が今すぐ取り組むべき10の改革 ―
はじめに 企業価値は【内部の透明性】で決まる
スタートアップのベンチャー企業や後継者不在の中小企業にとって、事業の売却は重要な将来の選択肢です。事業承継型M&Aやスタートアップのイグジットが現実的に動き出したときに、「高く売れる会社」と「買い叩かれる会社」の差は、経営の仕組みが整理されているか、属人的なものになっていないか、という観点から生まれます。
法務(特に労務)や財務の整備がなされていない企業は、業績が良好だとしても思わぬ評価減を受けるリスクがあります。逆に、内部が整っている企業は「安心して引き継げる会社」として、複数の買い手から高値が提示されることが見込まれます。
M&Aの直前ではなく、その手前で実施することができる諸施策(プリ・デューデリジェンス支援)について、弁護士、税理士、公認会計士といった専門家の視点で、以下、解説します。
Ⅰ.労務・ガバナンスの整備 ― 潜在リスクの可視化
1.各種社内規程・協定の見直し
会社設立時に策定して以来、整備が遅れがちな「就業規則」「賃金規程」「退職金規程」などに加えて、以下のような規程も、改訂の対象となります。
- 人事考課規程、服務規律規程、懲戒規程、休職規程【運用実績があるかどうか?】
- テレワーク勤務規程、副業規程、育児介護休業規程【特に、最近の改正を反映しているか?チェックが必要です。】
- 安全衛生規程、労働安全管理規程【実務の運用と一致している?産業医との契約は適切?】
- ハラスメント防止規程、内部通報規程【社内研修と連動させる必要があります。】
最新の労働法改正(働き方改革関連法、パワハラ防止法など)への対応を行い、潜在的な未払賃金リスクや不適正な人事運用を是正します。
2.労使協定と残業リスクの洗い出し
36協定や変形労働時間制協定の実態を精査し、過去の勤怠データから未払残業の可能性を把握します。「我が社ではもちろんタイムカード通りに残業代はちゃんと支払っている」これだけではリスクは解消できません。昼休憩が取れているかどうか、直行直帰の営業社員の労働時間管理はどうしているか、といった複数のテーマで監査が必要です。これによって、買収時の「潜在債務」を定量的に把握することができます。
3.ハラスメント対応体制の整備
パワハラ・セクハラなどの潜在的被害を放置すると、訴訟リスクとして減額評価を受けます。ハラスメント委員会や相談窓口の設置は必須ですし、調査・是正のフローを明文化し、外部通報窓口を併設することで、安心感と企業価値を高めます。
4.人事評価制度・研修体系の整備
人材が定着し、継続的に成果を出せる体制を整えることで、買い手に「再現性のある経営」を印象づけることができます。また、ここで「同一労働・同一賃金」の原則に反した運用がなされていないか、というチェックもできます。これは未払賃金の請求リスクの把握につながります。
これまでの人事評価資料を確認します。また、研修計画を企画・立案し、運用することが必要となります。
Ⅱ.財務の整備 ― 信頼性の高い決算へ
5.未回収債権・未収金の整理
非常に典型的な内容となりますが、意外と顧問税理士から指摘されていても、長年放置しているケースが多いのが、古い売掛金や未収入金の問題です。
そのまま放置していると、将来の財務デューデリジェンスで「不良債権」として評価減となることは明らかです。債権管理台帳の整備、回収方針の策定・運用が重要です。
6.役員貸付・仮払金の精算計画
上場時に必ず指摘される代表者と法人間の貸借関係の有無は、買い手が最も警戒するポイントです。返済計画や債権放棄スキームなどを事前に整理すると、数年かけなければ解消できないということもあり得ます。また、税務上の負担関係・リスクも確認します。
7.棚卸・固定資産の評価整理
資産の適正な評価を実地棚卸・減損処理により実施し、実態と合致した貸借対照表を作成します。こうした作業により信頼できる決算書を提示することが、売却交渉の前提になります。
8.会計方針・経理フローの文書化
中小企業では、経理業務については担当者が一人で見ているためにブラックボックス化してしまっていて、新たに人を採用した時に抱えていた問題が浮き彫りにされてしまう、といったことがあります。信頼しているからこそ見ていない、という経営者の心理こそがリスクを増大させてしまいます。
経理処理の属人化を防ぎ、月次決算の流れや承認権限を明確化することで、企業の内部統制水準を示します。
Ⅲ.法務・情報管理の強化 ― 信頼を得る内部体制へ
9.契約書・知的財産の整備
契約書の雛形の使い回しや、相手会社の契約書をそのまま受け入れている企業では、思わぬ落とし穴が契約関係に潜んでいます。そもそも契約書を作っていない場合はもちろん、改正された下請法(取適法)やフリーランス新法への対応などはできているか、弁護士の目線での確認は必要不可欠です。
取引基本契約書、NDA(秘密保持契約書)、業務委託契約やサービスの利用規約などの見直し、更新を行い、更に電子契約化を推進します。
また、商標、著作権、開発ソースコードの帰属を明確化し、各種特許について申請の要否を整理、知財デューデリジェンスで減点を受けない体制を構築します。
NDA(秘密保持契約)の整備・運用ポイントは、こちらの解説をご参照ください。
10.個人情報・機密情報管理と取締役のコンプライアンス
個人情報保護法、不正競争防止法に基づく社内ルールを整備し、アクセス権限管理・持出制限などの運用を明確化します。
さらに、取締役・役員の競業避止義務・利益相反取引に関する管理体制を確認・整備し、ガバナンス体制を【上場水準】に近づけます。
そのためにコンプライアンス委員会を設置し、将来のリスクに早めに対応できる体制を設けるのがベターです。
まとめ 内部を磨けば、企業価値は跳ね上がる
「高く売れる会社」とは、単に業績の良い会社ではなく、誰にでも【安心して引き継げる会社】です。 経営者が変わっても従来通りにやっていればうまくいくと言えるだけの法務、財務、情報管理の体制を整えることは、将来のトラブルを防ぐと同時に、企業の信頼性を高め、結果的に売却価格の上昇に直結します。
貴社の現状を診断し、最適な整備計画をご提案いたします。 M&A前の法務・財務デューデリジェンスに備えた「磨き上げ支援」は、弁護士法人本江法律事務所までお気軽にご相談ください。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。