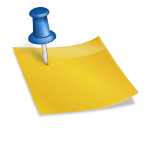有給休暇とは?
有給休暇は、労働基準法第39条に基づいて、一定の条件を満たした労働者に付与される法定の休暇です。これは、労働者が給与を得ながら休暇を取得する権利を保障するもので、心身の健康維持や生活の充実に寄与する重要な制度です。企業の経営者や人事担当者は、この制度の正しい運用を理解し、トラブルを未然に防ぐ必要があります。
有給休暇の付与日数
労働基準法第39条によると、有給休暇の付与条件は以下の通りです。
継続勤務期間:6か月以上継続して勤務していること。
初年度は直近の6か月間、その後は直近の1年間に継続勤務していることが必要です。
出勤率:全労働日の8割以上出勤していること。
業務上の病気やけがの治療のために休業した期間や産前産後休業の期間、育児・介護休業の期間及び有給休暇を取得した日は、出勤したものとみなされます。
付与日数は勤続年数によって異なります。
| 勤続年数 | 年間付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
企業は、従業員から有給休暇の日数について尋ねられた時に、この法定の計算上の日数を下回る日数で回答することのないように注意する必要があります。
有給休暇の繰越ルール
未使用の有給休暇は、次年度に繰り越すことが可能ですが、その有効期限は付与日から2年間です。この期限を超えると失効するため、従業員には計画的な取得を促すことが重要です。
計画的付与制度の活用も推奨されます。この制度では、企業が従業員の同意を得た上で有給休暇の取得日を計画的に指定できます。特に繁忙期を避けた効率的な運用が可能になります。
有給休暇を巡るトラブルとその対応
有給休暇に関するトラブルは多岐にわたります。以下はよくある例とその対応策です。
-
取得申請の拒否
-
法定の範囲内での有給休暇申請を企業が拒否することは労働基準法第39条1項に違反する行為として、認められません。違反には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
-
運営上の理由で日程調整が必要な場合、使用者は「時季変更権」を行使することができます。もっとも、一方的に時季変更を申しつけるのではなく、別の日に取得してもらうように労働者との間で話合いを行い、解決するようにしましょう。
-
-
年5日の有給休暇を取得させる義務に違反
-
事業者は、有給休暇が年間10日以上付与される従業員に、時季を定めて年5日の有給休暇を取得させる義務を負います(労働基準法第39条7項)。これに違反した場合、30万円以下の罰金の対象となります。
-
-
有給休暇の買取・買上げ
-
未使用の有給休暇を消化させないために買い上げることも違法です。これについても、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
-
但し、取得しないまま時効にかかった有給休暇の買い上げや、退職前に消化できなかった日数分の買い上げは、例外的に認められています。
-
経営者・人事担当者へのアドバイス
-
有給休暇管理のシステム化
-
デジタルツールを活用して、有給休暇の残日数や取得状況を明確に管理しましょう。
-
-
従業員への説明責任
-
有給休暇のルールや取得方法を、従業員に分かりやすく説明するための研修や資料を準備してください。
-
-
トラブル時の専門家相談
-
万が一トラブルが発生した場合は、労務に精通した弁護士や社会保険労務士に相談することで、迅速な解決を図ることが可能です。
-
まとめ
有給休暇は、労働者の権利を守りつつ、企業の健全な運営を支える重要な制度です。適切な運用を心がけることで、労使間の信頼関係を築き、職場環境の改善につなげることができます。お困りの際は、弁護士法人本江法律事務所までお気軽にご相談ください。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。