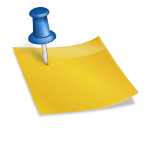1.競業避止義務とは
競業避止義務とは、従業員や企業の役員が、在職中または退職後において、使用者と競合する業務を行わない義務をいいます。
在職中の従業員が競業避止義務を負うことは雇用契約上の付随義務として、学説や裁判例においても一般的に認められています。また、取締役については、会社法356条1項1号が会社の承認なく競業取引ができないという形で在職中の競業避止義務が定められています。
使用者側が役員・従業員に競業避止義務を課す目的は、競合する事業者に自社の機密情報が漏えいしたり、取引先を奪取されたりしないようにして、自社の競争上の優位性を確保することにあります。
そして、競合に知られては困る機密情報や取引先との関係性などは、退職した元役員や元従業員も把握しており、退職して直ぐに競合する事業者に就職されたり、直ぐに競合する事業を自ら立ち上げられてしまうと、機密情報の漏えいや取引先の奪取を許すことになりかねず、企業として競争上の優位性を確保するためには、元役員・元従業員にも競業避止義務を課す必要があります。
しかし、退職後に元従業員・元役員が競業避止義務を負うか否かということについては、法令上の根拠が定められていません。
そこで、企業がどのような方法が取り得るのかが問題となります。
2.退職後の競業避止義務が認められるには
元従業員や元役員は、原則として退職後は職業選択の自由があり、自らの経験やノウハウを活かした仕事をすることも、当然に禁止されるものではありません。
そこで、企業としては、就業規則や個別に取り交わした誓約書により、退職した元役員・元従業員に競業避止義務を認めさせることが考えられます。
裁判例には、「被用者に対し、退職後特定の職業につくことを禁ずるいわゆる競業禁止の特約は経済的弱者である被用者から生計の道を奪い、その生存をおびやかす虞れがあると同時に被用者の職業選択の自由を制限し、又競争の制限による不当な独占の発生する虞れ等を伴うからその特約締結につき合理的な事情の存在することの立証がないときは一応営業の事由に対する干渉とみなされ、特にその特約が単に競争者の排除、抑制を目的とする場合には、公序良俗に反し無効であることは明らかである」と判示したものがあり(奈良地判昭和45年10月23日)、先例的な意味合いが認められています。
つまり、元従業員・元役員に対し、退職後も競業避止義務を課す「特約」を締結する際には、その制約を課す合理的な事情の立証が必要です。『合理的な事情』としては、目的が競争者の排除・抑制に留まらず、機密漏えい防止といった正当な利益にあるということを立証することが必要になります。
退職後の競業避止義務を定める手段として、単純に『就業規則では不十分』ということではなく、就業規則による制限の仕方が合理的かどうかが重要、ということです。
もっとも、競業避止義務の定めが合理的として有効になる為に検討されるべき後述の要素(要件)を見ると、退職者の地位・業務内容や代償措置といった事情が重要であり、これらは退職時でなければ『相当かどうか』が判別し難いことや、就業規則で規定しているとしても適用対象が限られると思われることからすれば、やはり退職時に改めて代償措置の程度も含めて検討し、誓約書で競業避止義務を課すという運用の方が実務的には問題が生じにくいと思われます。
3.退職後の競業避止義務が有効となる要件
退職後の競業避止義務を定めた就業規則や誓約書などの個別の合意が有効とされるためには、使用者側の正当な利益を保護しつつ、従業員の職業選択の自由に対して配慮した内容にする必要があります。
これまでの裁判例の傾向として、認容事例の割合は極めて低いと言えます。すなわち、退職後の競業避止義務について明文の定めがあるケースでも、公序良俗違反で無効という判決がなされることがほとんどです。ただ、そのような認定に至る理由は裁判例においても明確に述べられていることから、以下の要件が重要なポイントであることが分かっています。
1. 守るべき使用者側の利益
競業避止義務が正当化されるためには、上述のように、その目的が企業が保護すべき「正当な利益」を守ることにあると認められることが必要です。
企業が保護すべき「正当な利益」とされるものとしては、営業上、技術上、経営上の機密情報(営業ノウハウ・営業戦略・収益構造、製造技術、部品等調達先、経営方針など)の保護という利益が挙げられます。また、企業として既存顧客を維持することも「正当な利益」ということはできます。
但し、重要なのは、このような目的を阻害するような競業避止義務違反行為がなされたと言えるのか、ということが問われるという点です。
例えば、機密情報の保護が目的ということであれば、「機密情報を競業会社に提供する行為」が禁止されれば足りるところ、そのような限定もなく、単に競業会社に就職すること自体を禁止することは、職業選択の自由に対する過度な制約として無効になり得るということです。
2. 競業避止義務を課す従業員の地位
全ての従業員に対して競業避止義務を一律に課したとして、職業選択の自由の観点から、その中の特定の従業員との関係では公序良俗違反として無効となり得ます。そこで、義務を課す対象となる従業員の地位や職務内容を慎重に選定する必要があります。
企業経営の中枢にいる取締役や経営戦略部門の幹部、研究・開発部門で技術的な機密情報を取り扱う者などに対しては、競業避止義務が認められやすいと考えられます。
これに対し、機密情報を取り扱わない事務職員や現場の作業員など、機密情報の保護や既存顧客の維持といった利益に関与しない者については、競業避止義務が認められない可能性が高いと思われます。
ここでも競業避止義務を課すことで具体的に守りたい利益を特定しておくことが極めて重要です。
3. 地域的な限定を付すこと
競業避止義務を負う地域的な範囲を設定することは、義務が有効と扱われるために重要です。
例えば、元の使用者の営業エリア(県内や市内、近隣の県など)に限定する、あるいは主要な顧客が集中するエリアに限定する、といった形で、職業選択の事由が過度に制限されないように配慮することで、競業避止義務が有効と認められやすくなります。
4. 競業避止義務の存続期間
競業避止義務の存続期間は、合理的な範囲に設定する必要があります。
一般的には「1~2年」程度までに抑えるべきと言ってよいでしょう。3年以上となると、無効となるリスクが大きく高まると考えてよいと思います。
5. 禁止される競業行為の範囲
競業避止義務が適用される「競業行為」を限定することは、競業避止義務を有効と認められるためには必要と考えられます。
例えば、禁止される就職先を業種・職種で限定する(例えば、単に「同業他社」「競合する事業者」などと記載するのではなく、「システム開発業」や「建築工事業」などの業種、「技術職」や「営業職」といった職種まで記載する。)ことが考えられます。
競業行為の限定に際しては、競業避止義務の目的が機密情報の保護であれば、機密情報の漏えいに繋がり得る行為に限定する、といった配慮をすることにより、退職者の就職活動に対する過度な制限とならず、有効と認められやすくなります。
6. 代償措置の必要性とその内容
競業避止義務を課す場合、従業員の職業選択の自由を制限することになるため、代償措置(補償)を設けることが求められます。特に、競業避止義務の範囲が広く定められている場合(地域が広い、年数が長いなど)ほど、補償の必要性が高くなると考えられます。
具体的な代償措置として、退職金の上乗せ(算定基準による額に増額する。)、退職前の一定期間の給与増額(退職前の6か月間、給与を増額する。)などがありますが、競業避止による収入補償として支給がなされたことを明らかにするため、誓約書等に代償措置についても定めを置くべきだと思われます。
4.競業避止義務違反に対する損害賠償請求の内容
競業避止義務に違反して元従業員が競争相手に転職したり、独立して競業行為を行った場合、企業は損害賠償請求を行うことができます。その際、主に「逸失利益の賠償」や「違約金の請求」が問題となります。以下、それぞれの計算方法や注意点について詳しく解説します。
1. 逸失利益の計算方法
競業避止義務違反に対する損害賠償請求においては、主に「逸失利益」(本来得られたはずの利益)が請求の対象となります。
例えば、元従業員の競業行為によって、自社顧客が奪われた場合、その顧客との取引による利益が失われることが損害となります。
このような「失注による逸失利益額」は、次のように求められます。
逸失利益 = 競業行為により失注した顧客との取引の売上(過去の実績) × 営業利益率(原価を差し引いた実績の利益率)
例えば、失注した取引の前年までの売上が、平均して年間1,000万円で、営業利益率30%という場合、逸失利益の額は年間で、
1,000万円 × 30% = 300万円
となり、競業避止義務の期間(2年間なら2年分)に相当する金額を請求することになります。
2. 違約金を定めるときの注意点
競業避止義務違反を防止するために、誓約書などに違約金を定めておくことも有効です。
但し、違約金があまりに高額だと公序良俗違反として無効になる可能性があるため、適正な設定が求められます。
(1) 違約金の設定方法
想定される損害額を基準として設定することが一般的です。
例えば、当該従業員による機密漏えいを想定し、それにより競合する事業者が自社と同等の製品開発やサービス展開を行うに至った場合に減少する利益額を想定する、当該従業員が担当する顧客が他社に流れたことで減少する利益額を想定する、といった形です。
一方で、代償措置を提供している場合には、その返還を求めるという形も考えられます。
(2) 過去の裁判例から学ぶ
裁判例では、違約金として、退職金の半額+給与の6カ月分としていた事案において、退職金の半額+給与の1か月分の限度で違約金請求権を認めた事例があります(東京地判H19.4.24)。
この裁判例においても、定められた違約金の条項に基づく請求が認められるかどうかは、現実に行なわれた競業行為がどの程度のものであったかを踏まえて判断されています。
5.よくある質問(FAQ)
Q1. 就業規則で「退職後3年間は同業他社への転職を禁止」と定めていますが、有効ですか?
A. 裁判例の傾向からすれば、「3年間」という長期にわたる制限や「同業他社」という記載の仕方は、公序良俗違反として競業避止義務の条項を無効とする可能性が非常に高いと考えられます。
仮に代償措置(補償)を設けたとしても、裁判では無効と判断されるリスクがあると考えて良いでしょう。
Q2. 一般職の社員にも一律で競業避止義務を課したいのですが、問題ないでしょうか?
A. 企業の営業秘密や顧客情報に直接アクセスしていない社員にまで一律で課すと、過度な職業制限として無効となる可能性があります。情報へのアクセス度合いや職務内容を考慮して範囲を限定することが大切です。
6.競業避止義務が問題となるケースは弁護士に相談を
退職後の競業避止義務にまつわる問題は、企業の利益や従業員の将来に重大な影響を与えます。特に、顧客の引き継ぎや営業秘密の流出など具体的な損害が発生した場合は、早期に法的手段を検討すべきです。
是非お気軽に当事務所までご相談ください。就業規則や競業避止義務に関する誓約書等の整備、損害賠償請求や差止請求を視野に入れた対応を講じることができます。
実際の紛争が起きてからではなく平時において、弁護士の支援の下で事前の備えを徹底しましょう。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。