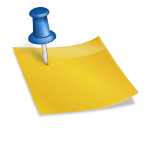1 はじめに
近時、従業員により退職代行サービスが広く利用されるようになり、企業側は突然の退職通知に直面する機会が増えています。特に2025年10月、退職代行業者「モームリ」と提携していた法律事務所が、弁護士法72条違反(非弁提携)の疑いで家宅捜索を受けたことは、退職代行ビジネスの適法性に重大な疑義を生じさせるものでした。
本稿では、企業経営側が押さえておくべき法的枠組みと、実務対応を詳細に解説します。
2 退職代行サービスの類型と適法・違法の境界
退職代行は大きく分けると、①民間企業型、②労働組合型、③弁護士型に分類されます。
① 民間企業型の退職代行ができることは、退職の意思通知に限られます。それを超えて「退職条件の交渉」、「有給消化」、「未払賃金の請求」などの法的要求に立ち入った場合、非弁行為となる可能性が高いと思われます。しかし、実際には、「私どもは単なるメッセンジャーであって、交渉をするつもりはない。本人の意向を伝えるだけです。」などと言って、法的な交渉を仕掛けてくることがあります。
② 労働組合型の退職代行は、団体交渉権に基づき上記のような法的交渉も認められますが、中には実態の乏しい組合も存在し、形式だけ組合を名乗る事業者もあるため注意が必要です。
③ 弁護士による退職代行は、退職の通知を超えた法律業務も適法に行えますが、民間業者と連携し、その送客手数料を受け取ることが非弁提携となり得るため、これもスキーム次第では違法性が生じることになります。
3 弁護士法72条と非弁行為・非弁提携の分析
弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で(中略)一般の法律事件に関して(中略)法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めています。
ここにいう「法律事務」とは、代理や和解はもちろん、法的アドバイスや法的主張を含む文書作成なども含まれると考えられます。
そして、民間企業型の退職代行による「非弁行為」の典型例としては、退職時の有給取得や買取り交渉、有給取得目的での退職日の調整、未払賃金請求、解雇通知の撤回交渉などが挙げられます。これらを弁護士でない業者が有償で行えば明確に違法となります。
また「非弁提携」とは、法律事務所が報酬目的で非弁業者に利用され、紹介料を授受することで成立し、弁護士側にも重大な責任が生じます。最近の摘発では「弁護士監修」を名目に実質的な提携があったケースも問題となっています。
4 モームリ事案の概略と実務上の示唆
報道によれば、モームリの運営会社は、提携する法律事務所に退職者を紹介し、紹介料(キックバック)のやり取りをしていた疑いが持たれたようです。法律事務所との間に実体のない労働環境改善組合という組織を介在させ、そこに紹介料という名目ではなく賛助金という形で金銭を支払うことで、実質的に紹介料の支払いを行っていたと疑われたとのことです。
この一件で、民間退職代行業者と弁護士の関係性は世間から厳しく問われるようになりました。
特に、企業側にとって重要なのは、退職代行が交渉を要求してきたときに、相手方の交渉が適法に行われているかどうかを判断する視点を持つことです。交渉相手の違法性を見抜くことができないと、結果として企業は誤った合意を余儀なくされるおそれがあるからです。
5 退職代行から連絡が来た際に企業が確認すべき5点
退職代行から連絡がきたときは、まず次の5点を確認しましょう。
① 連絡者の属性 民間企業/労働組合/弁護士
どのタイプの退職代行かは、交渉に応じて良いかどうかの判断の前提となります。
② 退職の意思表示として退職日を有効に指定しているか
退職日がはっきりしなければ、有効な退職の意思表示として取り扱うことが困難となります。
③ 退職について何らかの条件提示をしているか
何らかの条件付きの退職ということは、交渉をしてきているということになります。
④ 本人からどういった委任を受けたか、それを証明できるか
退職代行が本人から何についての委任を受けているのか、それを文書などで証明できるかは重要です。
⑤ こちらから本人に直接連絡することができるかどうか
本人の意思確認や退職に際して行うべき引継ぎ、貸与物返還など、様々な事項について本人と連絡を取れるのかどうかは重要です。
但し、本人への連絡がハラスメント行為として問題視される可能性があるので、注意が必要です。
6 使用者側が避けるべき対応
退職代行業者に対する不信感から、感情的になって一切の要求を拒絶するといった対応は誤りです。
一方で、悪質な業者と交渉をすることは避けるべきで、そのような場合にはあくまで本人との交渉には応じる、といった姿勢を貫くべきです。具体的には、「退職を通知するという伝達を超えた法的な要求や交渉は、権限のある方との間でなければ、当社として応じるわけには参りません。本人か、代理権のある弁護士からの連絡をお待ちしています。」といった形で、門前払いするべきでしょう。
では、そのような対応をしたときに、業者から紹介されたと思われる弁護士が登場した場合にはどのように対応したらよいでしょうか。これは非弁提携の弁護士かもしれません。そうだとすれば、上述のように弁護士法上の問題を抱えていますが、かといって本人からの授権まで一律に否定されるものではありません。つまり、本人からの委任があれば、交渉相手としては適切です。したがって、その場合には弁護士との関係で退職の条件交渉を詰めることになるでしょう。
7 退職代行利用が増える背景
これまでとは特に若年層の価値観が変化してきたことで、緊張関係にある当事者間の対面は忌避される傾向が明白になっています。と言っても若年層に限らず、職場コミュニケーションの希薄化により、摩擦に耐えられない、耐える価値を見出せないという従業員は増えています。
企業は、これを単なる「代行ブーム」と捉えるのではなく、若年層の働き方観や心理的安全性の課題として認識する必要があります。このような情勢を理解すると、現在のコンプライアンス遵守のために、メンタル不調者の早期発見のためのストレスチェック、従業員支援制度(EAP)の導入、外部通報窓口の設定などの体制整備が求められることと繋がります。
8 企業として講じるべき予防施策
企業としては、このような情勢に対応するために、就業規則において現実的な退職手続を整備するべきで、退職代行にも対応できる退職フローを標準化することが必要です。また、ハラスメント対策、メンタルヘルス対応の強化などにも取り組むことで、紛争発生を事前に回避することにもつながります。
9 まとめ
退職代行は今後も増加するでしょうが、企業が適切な法的対応を行う限り、企業に対して特に実害を与える存在ではありません。とはいえ、実務においては常にイレギュラーな事態が起こり得ることを想定すると、退職代行からの連絡に際しては、即座に相談できる顧問弁護士を確保しておくことは重要です。顧問弁護士の適切なサポートを早期に受けることで、トラブルも最小限に抑えることができ、健全な労務管理を維持することができます。
弁護士法人本江法律事務所は、数多くの労務問題に企業側で取り組んできた実績に基づき、特殊な事案においても適切なアドバイスと実際の対応を任せていただくことができます。お気軽にお問合せ下さい。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。