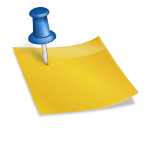1.退職合意書とは
従業員の退職に際して、会社は、その従業員の在職中に発生した会社との間の債権・債務を整理し、退職後においても義務や制限を課す必要がある場合、これらを明確にするために退職合意書が作成されます。
この退職合意書は、口頭のやり取りや退職届だけでは不十分な「退職後の紛争リスク」の回避を目的として作成するものなので、退職後にどういった紛争が起こりやすいかを踏まえておく必要があります。
2.退職合意書を作成するべき状況とは
従業員が退職するとき、どのような状況においても退職合意書が必要というわけではありません。
何の問題もなく退職していく従業員が大半であるところ、退職合意書を作成する必要性があると思われる状況とはどういう状況なのかをあらかじめ把握しておく必要があります。
典型例として3つのケースで退職合意書の作成が必要となります。
(1)退職勧奨によって退職するケース
一定の問題がある従業員に対し、自主的な退職を要求する「退職勧奨」を行った結果として、従業員が退職に応じる場合、退職日や退職理由の他、退職の条件などを合意書に明文化することが必須です。退職合意書を作成しない場合、退職後に従業員から「退職を強制された」とか、「解雇された」といった主張が出てくる可能性があります。
(2)退職後に未払残業代など何らかの金銭請求をする可能性があるケース
退職後の従業員が会社に対して、未払いの賃金や残業代を請求し、あるいはハラスメント行為を理由とする損害賠償を請求するなど、様々な金銭請求を行うことが見込まれる場合には、退職合意書にいわゆる「清算条項」として請求権など会社が負う債務が存在しないことを確認・合意しておくことが有効です。この時に、「未払賃金債権」「貸与品返還債務」など考えられる債権債務を列挙し、それらが既に存在しないことを明記することができれば、そのように記載する方がベターだと思われます。
(3)退職後に競合他社に就職することが見込まれるケース
従業員が退職した後に、会社の技術情報や顧客情報などを社外で利用する可能性がある場合には、退職後においても守秘義務や、競業避止義務、顧客に対する営業の禁止などを合意書において明文化することが有効です。但し、競業避止義務を課す場合には、その義務に見合った代償措置を講じることなど、従業員の職業選択の自由に対する十分な配慮が不可欠です。
3.紛争化を防ぐための退職合意書の記載の仕方
(1)退職後の未払賃金請求権などの行使を防ぐための条項
例えば、次のような条項の場合に、どのような問題が生じ得るでしょうか。
「本合意書に定めるもののほか、何ら債権債務が存在しないことを相互に確認する。」
この条項で合意締結したにもかかわらず、退職した労働者が未払賃金請求権やパワハラ等を理由とした損害賠償請求権を行使してきた(訴訟提起をしてきた)ために、使用者側が上記条項により債権は放棄された、という反論をしたとします。
その場合、裁判所は、退職時にどのようなやり取りがあったかを具体的に明らかにするように求めた上で、未払賃金の請求やハラスメントの存在などが交渉の中に出てきていなかったのであれば、この条項があったとして、労働者側が未払賃金請求権などを放棄する意思があったとは言えない、と判断する可能性が高いと思われます。
そこで、使用者側としては、次のように存在が疑われる請求権を敢えて記載し、この条項が労働者側の権利放棄の意思を裏付けるものと認められるようにしたいところです。
「本合意書に定めるもののほか、未払賃金請求権や損害賠償請求権その他の一切の債権債務関係が存在しないことを相互に確認する。」
もちろん、使用者から見ると、この記載を見て労働者が未払賃金の存在に気が付いてしまうリスクがあるということになりますが、気が付いて当然だからこそ債権放棄の効果が認められる可能性が高いと言えます。
(2)退職後の競業・顧客奪取を防ぐための条項
退職した労働者が競合する会社に転職したり、または近い地域において独立開業する等して、既存顧客を奪取することを防ぐための条項として、例えば次のような条項が用いられることがあります。
「退職後3年間は、同業他社への就職、役員への就任、自ら又は第三者をして同種事業を開業し、若しくは同業他社を設立してはならないものとする。」
退職後における競業避止義務は、退職後の競業避止義務を規定した就業規則や退職合意書等において定められなければ、義務として当然には生じません。そのため、退職従業員による競業及び顧客奪取の危険性がある場合には、退職合意書において競業避止義務を設けておくことが必要です。
しかし、退職後の競業避止義務は、合意等があったとしても必ずしも全てが有効になるわけではありません。
上記条項についても、これが従業員の職業選択の自由を過度に侵害するものであると評価されてしまうと、裁判所によって無効とされるおそれがあります。
裁判所が競業避止義務条項の有効性を判断する際に考慮する要素としては、①使用者側の具体的な利益、②退職者の在職中の地位・職務の性質、③競業避止の期間、地域、対象業務・範囲、④代償措置の有無・内容、⑤その他の事情です。
退職合意書の条項を記載する際に検討すべきは、③の期間、地域、対象業務・範囲ということになります。例えば次のようにこれらの要素を限定的に記載することで、競業避止義務条項の有効性が認められやすくなります。
「退職後1年間は、甲(会社)と同じ又は隣接する市区町村において、同業他社への就職、役員への就任、自ら又は第三者をして同種事業を開業し、若しくは同業他社を設立してはならないものとする。但し、甲の事業のうち、広告代理店業務以外の事業については、この限りではない。」
こういった形で、期間を2年以内に制限、地域は会社と実際に競合するエリアに制限することを有効性を高めるために検討すべきです。また、業務については、競業避止義務を課す目的との関係で問題になりますが、自由競争を前提とした取引社会において『顧客維持の目的』は裁判所には共感を得られにくいところがある印象で、むしろ競合との関係での『機密情報の保護』を目的にすることが理解されやすいと思われます。そういった目線からは、この労働者が特定の業務の『機密情報』に関与していたかどうか、という目線から、業務を限定しておくことは、競業避止条項全体の必要性・相当性を高めることであると言えそうです。
4.退職合意書の作成を弁護士に依頼すべき理由
退職合意書は、会社と元従業員との間で退職後に無用な紛争が生じないようにするための書面ですが、その目的を達成するためには、従業員において、後日、この書面に有効性がないと判断されないような内容とすることが必要と考えられます。
そのためには将来、退職後に生じる紛争を具体的にイメージして、そこから逆算して退職合意書を作成するべきで、紛争対応に熟達した弁護士だからこそ、このようにケースに応じた具体的な紛争回避のための条項案を作成する能力を備えていると言えます。
同じく労務関係を取り扱う社会保険労務士が豊富な知識を背景に退職合意書を作成するケースもありますが、紛争事案において代理人として交渉・訴訟を経験している弁護士とは、ケースごとの「特殊性」にどう対応するか、という目線が異なるように思われます。
当事務所は、特に使用者側で様々な労使関係のご相談や紛争での代理人対応を行っています。
従業員退職後の紛争にも多数対応をしてまいりましたので、クライアント企業の状況、従業員との関係性といった特殊性を踏まえつつ、経営者目線でのオーダーメイド退職合意書の作成は得意分野です。
お気軽にご相談ください。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。