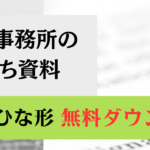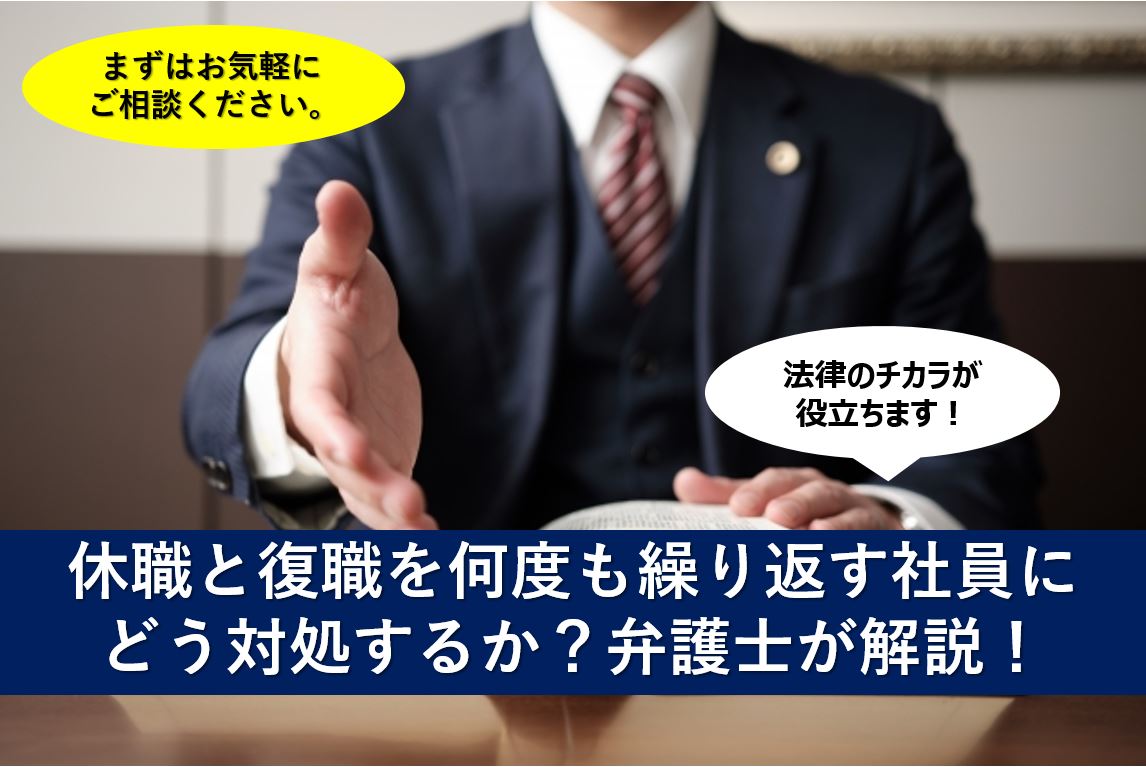1 改正前下請法の概要
下請法とは
下請法(正式名称「下請代金支払遅延等防止法」)は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位を背景とした不公正な取引方法を防止し、下請事業者の利益を守ることを目的としています。
下請代金の一方的な減額や、支払日の延期といったことが禁止され、その防止のために親事業者には様々な義務が課せられています。
適用対象となる取引
下請法が対象とする取引は、「親事業者と下請事業者との間」の取引のうち、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託(ソフトウェア開発委託など)及び役務提供委託という4類型に分類されます(以下、まとめて「製造委託等」といいます。)。
ここには、例えば建設工事は対象となっておらず、建設工事における下請事業者は、建設業法で保護が図られています。
そして、下請法の対象となる「親事業者」と「下請事業者」は、資本金を基準として、次のように決められます。
製造委託、修理委託、情報成果物作成委託のうちプログラムの作成・情報処理、役務提供委託のうち運送、物品の倉庫保管の場合
(A)資本金3億円超の「親事業者」→資本金3億円以下の「下請事業者」
(B)資本金1000万円~3億円の「親事業者」→資本金1000万円以下の「下請事業者」
上記を除く情報成果物作成委託と役務提供委託の場合
(A)資本金5000万円超の「親事業者」→資本金5000万円以下の「下請事業者」
(B)資本金1000万円~5000万円の「親事業者」→資本金1000万円以下の「下請事業者」
この資本金基準を踏まえると、上記製造委託等の取引に際しては相手当事者の資本金の把握は絶対に必要で、継続的な取引の場合には、増資や減資によって適用対象となったり、外れたりすることがあるので、注意が必要です。
親事業者の義務
下請法上の親事業者として対象取引を行う場合には、次のような義務を負います。
・発注の際は直ちに発注書面(法定の記載事項を記載したもの)を交付すること
・下請代金の支払期日を受領後60日以内に定めること
・取引記録の作成と、これを2年間保存すること
発注書面交付義務や取引記録の作成・保存義務に反した場合には、罰金の対象ともなります。公正取引委員会が定期的に調査・立入検査を行い、違反に対しては勧告・公表もなされることとなります。
禁止事項
上記の義務の他、下請事業者の利益のために、親事業者には様々な禁止行為が定められています。
買いたたき
下請代金の額を通常の価格水準より著しく低い金額に、不当に定めることを「買いたたき」と言い、禁止されます。
その要件は次の通りです。
①通常の対価と比べて著しく低い対価であること
②十分な協議を行わないなど不当に定めること
納品後に価格交渉を行い、見積書の金額を大幅に下回る単価を一方的に決定したり、緊急に短い納期での発注に応じることでコスト増が想定されるのに、そのコストを考慮しない単価で下請代金の額を決められてしまうなど、単に「著しく低い」だけでなく、その決定プロセスが「不当」と言えるかどうかがポイントです。
下請代金の減額
買いたたきに該当しない場合であっても、発注書面に記載した金額からの減額や、協力金の差引、価格を据え置いての納入数量の増加など、実質的な下請代金の減額を行うことは、禁止されます。
その他
その他にも、親事業者による支払遅延、受領拒否、不当返品または不当な経済上の利益の提供要請(不明瞭な協賛金の提供依頼など)など、下請事業者に対して不利益が生じるような取引行為は禁止されます。
2 改正後の下請法(取適法)の概要
近年、急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇によって、経済的に弱い立場にある事業者には、そのあおりを受けるリスクが高まっています。それは物価上昇の局面においても賃上げができない原因ともなり得るところ、サプライチェーン全体で「構造的に」価格転嫁を実現していくことにより、労働者の賃上げの原資を確保することが重要です。
「悪しき商慣習」を打破して「適正な価格転嫁」を定着させるという観点で、取引の適正化を一層推し進めるために下請法が改正されました(令和7年5月16日成立、同月23日公布)。
法律名・用語の変更
そもそもの法律名が変更となり、「下請代金支払遅延等防止法」から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、通称「中小受託取引適正化法」へ改称され、略称「取適法」となりました。
ここには「下請」という従属的なイメージからの脱却により、委託側と受託側が対等なパートナー関係にあることが意識されています。
これに伴い、各条項における用語も変更され「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更されました。「下請代金」は「製造委託等代金」となっています。
施行日と今後のスケジュール
施行日は、公布と同時に施工された一部規定を除き、令和8年1月1日とされています。
本校執筆時点では、未だその運用基準は公表されていませんが、令和7年10月頃に改正後の運用基準についても正式に公布される予定です。
なお、経過措置として、施行前に締結された契約についても、施行日以降は新法の適用があるため、対応が必要となります。
改正の概要
下請法の改正の目的は、上記のとおり、適正な価格転嫁とそのための交渉環境の整備にあり、下請事業者=中小受託事業者の保護が強化された形です。
主な改正内容として、適用対象の拡張、価格協議の義務化、手形払いの禁止、執行の強化といったことが挙げられます。
以下、順に解説していきます。
3 適用対象の拡張
親事業者・下請事業者の区分に従業員基準を導入
取適法は、上記の資本金基準に加え、従業員数基準を新設しています。
資本金基準は、現実には企業規模として大きいにもかかわらず、資本金が基準に達していないという理由で適用対象外となることがあるとの指摘を受けていました。そこで、製造委託では、委託事業者が従業員300人超、中小受託事業者が300人以下の場合には適用対象とし、役務提供・情報成果物製造委託等では、100人を基準としました。
従業員の人数にカウントされるのは「常時使用する」従業員に限られますが、これは賃金台帳に「常時使用される労働者」と分類されている従業員を想定しており、パート、アルバイト、短期労働者、使用期間中の従業員などでも、その実態として継続的な雇用関係があると判断できる場合には含まれる可能性があります。
適用対象の取引に「特定運送委託」が追加
改正下請法は、発荷主が運送事業者に対して顧客への物品の運送を委託する取引を「特定運送委託」として、既成の対象に追加しました。
その背景として、物流事業者が荷役や荷待ちといった役務を無償で提供させられている実情があります。
運送の委託については、既に独占禁止法に基づく物流特殊指定(正式名称:特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)という告示により、荷主による優越的地位の濫用に対する規制がなされてきましたが、これに加えて発注書面の交付や60日以内の支払期日などが求められることになります。
「金型以外の型等の製造委託」が追加
物品等の製造委託については、物品製造のための「型」等の製造のうち、従来の規制は、「金型」の製造委託のみが対象となっており、物品製造に必要な木型や樹脂型、工作物保持具などの製造委託は、規制の対象外でした。しかし、木型などもその物品等の製造のために使用され(密接関連性)、他の物品等の製造には用いることができない(転用不可)という点で異ならないことから、これらに関する製造受託事業者も保護されるべきということで、対象に追加されました。
4 価格協議の義務化
旧法でも買いたたきや下請代金の減額は禁止されていますが、改正法は、代金決定のプロセスにおいて下請事業者が求めたときは、親事業者は代金の額に関する協議に応じなければならないことを定めました。
公正取引委員会は、コスト変動の状況において、協議を経ない取引価格の据え置きが「買いたたき」に該当し得ることを運用基準として明確にしていました(令和6年5月)が、この改正は更に価格設定におけるプロセスの適正化を実現することを目的としています。
協議において必要な説明や情報提供を行う義務も認められ、一方的な価格決定という商慣習を改善し、様々な状況において従前の価格が適正とは言えない状況になったときに、中小受託事業者が価格について協議を求めることを奨励するもので、委託事業者に対するけん制ともなると思われます。
5 手形払い等の禁止
旧法では、代金支払期日までに割引を受けることが困難な手形の交付による決済を禁止していましたが、改正法は、手形払いを全面的に禁止するとともに、電子記録債権・ファクタリング等であっても、代金支払期日までに換価が困難であれば禁止されることとなりました。
従来の手形払いの慣行は、委託事業者による代金支払いの繰り延べのために、中小受託事業者が「割引」に伴う金利負担を余儀なくされるという実情があり、いわば委託事業者の負担すべき金利を事実上中小受託事業者が負担しているような構図となっていました。
手形払いの廃止という、既に政府が打ち出した方針を先立ち実現しつつ、さらに電子記録債権やファクタリングを用いる場合には代金支払期日前に満期日や決済日を設けることとすることによって、中小受託事業者にとっては、その資金繰りが改善し、手形等の利用に伴うコストの負担も回避することができるようになります。
なお、電子記録債権・ファクタリング利用に際し、委託事業者が満期日・決済日における割引料等を負担する合意の下であったとしても、支払期日より後に満期日・決済日が到来することは違法であるとされています。
また、下請法の運用基準改正案(令和7年7月公表)には、代金の現金振込時の振込手数料を中小受託事業者側の負担とすることは、事前の合意があっても本法違反であるとの方針が明示されています。
6 執行の強化
事業所管省庁(経済産業省や厚生労働省など、業種に対応する監督省庁をいいます。)は、従来、下請法に関しては調査権限があるにとどまり、是正等の関係では十分な権限がありませんでした。
それに対し改正法は、公正取引委員会、中小企業庁だけでなく、事業所管省庁も連携して下請法違反を取り締まることができるようにするために、事業所管省庁に指導・助言の権限を認めました。
また、下請事業者が事業所管省庁に本法違反の事実を申し出たときにも報復措置の禁止を定めることで、下請事業者の保護を図っています。
7 親事業者の実務的な対応リスト【チェックリスト】
- 契約書・発注書の用語を修正する
- 価格協議プロセスを文書化・記録化するための書式の整理
- 支払手段を現金(振込)に変更する、または電子記録債権・ファクタリングの満期日・決済日の設定についてルール化
- 全ての取引先の「従業員数」「資本金」を定期的に確認
- 特定運送委託・「型」製造委託の対象になるかどうかを確認
- 法改正に対応するための研修・社内周知を実施(令和7年中)
8 対応の詳細は弁護士に相談を
以上、改正下請法、取適法の概要について解説をして参りました。
チェックリストをご確認いただいたとしても、具体的な対応に際しては、個別の事情において悩ましい状況も多々あることと存じます。今後、各社が運用基準を丁寧に読み込み、対応を検討していく必要があります。
親事業者(委託事業者)の立場では、契約書・請求書等の文書修正に加えて、従前からの変更点を社内周知する研修の実施が喫緊の課題であり、専門家である弁護士にご相談をいただくべきことも多々あると思います。
他方、下請事業者(中小受託事業者)の立場でも、取適法に定める対応を実施していく上では、十分に法令の趣旨を把握した上で行動する必要があり、これには専門家の支援が不可欠ですし、取適法が施行される直前・直後は、取引ルールを是正する絶好のタイミングです。
私ども弁護士法人本江法律事務所の弁護士は、福岡近郊から京都大阪近郊までを対応エリアとして、下請法あらため取適法の適用を受ける可能性のある事業者様からのご相談には、委託事業者であっても中小受託事業者であっても、いずれも適切な対応を助言させていただくことができますので、是非お気軽にご相談下さい。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。