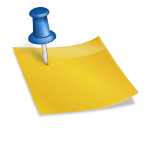スタートアップが知っておくべき役に立つNDA(秘密保持契約書)を弁護士が解説
スタートアップ・中小企業にとって、NDA(秘密保持契約)は単なる「秘密を守る書面」ではなく、取引機会・人材・事業価値を守る法的インフラです。本稿では、福岡を拠点とする顧問弁護士の視点から、NDAの基本、作成時のチェック観点、典型トラブル、そしてリーガルチェックの要諦まで、実務に直結する形で解説します。
契約書全般の作成・レビューの流れは
「契約書|作成・レビューのご案内」
にまとめています。NDA以外の雛形・チェック観点もご参照ください。
1 秘密保持契約とは
秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement, 以下では「NDA」と言います。)とは、主に企業間の取引に付随して取り交わされる秘密情報の漏えい等がないようにするため、相互の権利義務や、漏えい等の場合の対応やペナルティを定める合意のことを言います。
秘密情報の保護は、契約しなくとも、不正競争防止法において一定の保護が定められています。つまり、営業秘密の不正な取得や不正な利用に対しては、その営業秘密の保持者が差止請求や損害賠償請求をすることができるとされます(同法2条6項・7項等)。
不正競争防止法によって保護される「営業秘密」とは、「秘密として管理される」「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報」で、「公然と知られていない」ものがこれに当たります。
そうすると、「営業秘密」の定義に当たらない情報が漏えいしないようにしたいときや、「不正な利用」とまで言えない状況での漏えいに対して補償を求めるときなどのために、やはり個別にNDAを交わしておく必要性は高いものと思われます。
なお、秘密保持契約によって情報の保護を図ることは、不正競争防止法上の「秘密として管理」の要件を充足するために重要なポイントともなり得るものと考えられます。
2 秘密保持契約を作成するときに必要な観点とは
秘密保持契約を取り交わす際、自社が情報提供者か情報受領者か、という観点からチェックする必要があります。
(1)情報提供者の立場
まず、自社が情報を提供する側である場合、契約締結の目的である情報漏えいの防止が実現できるかが問題になります。
情報がどの範囲で守られるか、漏えい時に何ができるか(差止め請求、調査報告措置の要求など)、その後に何が求められるか(損害賠償請求、本体である契約の解除、再発防止措置)といったことが重要です。
要するに、取れる選択肢をなるべく多くし、相手のペナルティを明確に重くしておく観点になります。
(2)情報受領者の立場
これに対し、情報を受領する側に立つとどうなるでしょう。まず、受領した情報の全てが対象になるとすれば、管理責任が問われやすくなるため、できるだけ情報を限定して欲しい、ということになります。
また、損害賠償等の責任・ペナルティが重すぎるようであれば、それはできるだけ制限したい、ということにもなりますし、漏えい時の対応として取るべき措置も、予め決められてしまうよりも臨機応変に対応できる状況にしておきたい、といった観点が必要となります。
分野別の解説は
「契約書」カテゴリ記事一覧
から横断的にご覧いただけます。
3 秘密保持契約で特に注意すべきポイント
では、実際にNDAを作成・締結する際に、どのような点に注意すべきでしょうか。特にスタートアップ企業においては、技術情報や事業アイデアの保護が極めて重要である一方、相手方(投資家・共同開発先・業務委託先など)との関係も慎重に扱う必要があります。以下では、典型的な注意点を整理します。
(1)秘密情報の定義
最も基本かつ重要なのが「何が秘密情報にあたるのか」という定義です。この範囲が曖昧だと、いざ漏えいがあった際に契約上の保護を主張できないおそれがあります。
通常は、「開示の際に『秘密』である旨を明示した情報」(開示した後に『秘密』である旨を通知した情報も含む。)と限定する形が一般的ですが、スタートアップのようにスピード重視の環境では、こういった明示のアクションを失念することも少なくありません。
したがって、「口頭または書面その他の方法で開示された情報で、開示時に秘密である旨が明示されなかった場合であっても、本契約の目的または当該情報の性質上、秘密と認識できるものを含む。」といった文言を入れておくと、実務上の保険になります。
(2)秘密情報の利用目的
NDAの本質は、「開示目的以外に使用してはならない」という制約です。例えば、資金調達のために事業計画書を開示したのに、相手方がその情報を相手方企業の新規事業立ち上げに利用するようなことがあれば、自社の成長戦略を先取りされ、重大な損害につながります。
そのため、「本契約に定める目的以外には使用しない」という目的外利用の禁止はできる限り明確に。さらに社内共有範囲(部署・役職)を限定する等、運用まで書き込むのが有効です。共同開発・委託では目的を狭くし過ぎない現実的バランスも必要です。
(3)秘密情報の除外事項
一見保護範囲を広く取るほど安心に思えますが、実務的には「除外事項」を丁寧に規定することが重要です。たとえば次のような情報は通常、秘密情報から除外されます。
- 受領時にすでに公知の情報
- 受領後、受領者の責めによらず公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
- 開示情報によらず独自に開発・取得した情報
こうした条項がないと、受領者に過度の責任が課され、契約交渉が難航することもあります。
(4)漏えい時の対応と責任
万一の漏えい時には、速やかな報告義務・被害拡大防止措置・再発防止協議などのプロセスを明記しておくべきです。情報提供者側は、差止請求・損害賠償・本体契約の解除権まで選択肢を確保しておくのが望ましいでしょう。
(5)契約期間と存続条項
NDAは期間満了後も、秘密保持義務が一定期間存続するのが通例です。技術情報は概ね5年、営業情報は2~3年を目安に。将来の提携解消やM&A時に備え、終了後の取扱い(返却・消去・保管要件)も明確にしておきます。
4 スタートアップにおける典型的なNDAトラブルとその防止策
スタートアップ企業がNDAを締結する相手方として多いのは、「投資家(VC等)」と「業務委託先(開発会社・デザイナー・広告代理店等)」です。いずれも初期段階の事業推進には欠かせない関係ですが、秘密保持の観点からみると、想定外のトラブルに発展することも少なくありません。以下では、典型的な事例を通じて留意すべきポイントを整理します。
(1)投資家との間で起こりやすいトラブル
① NDAを締結してもらえないケース
資金調達の場面で、投資家がNDAを原則締結しない方針を採ることは珍しくありません。その場合は、段階的な情報開示(一般情報→限定情報)でリスクを抑制し、秘匿性の高い技術情報は投資検討の進度に応じた限定開示にとどめます。
② 投資家側の担当者変更による情報管理の不備
NDAを締結していても、担当者異動や組織変更で、データルームのアクセス権限が更新されず放置されることがあります。
予防策として、再提供・再委託の事前承諾義務、アクセス権限者の特定と更新義務、ログ管理等を契約で明文化します。
(2)業務委託先との間で起こりやすいトラブル
① 開発委託における再委託・持ち出しリスク
委託先が更に外部へ再委託する際、その再委託先にNDAが適用されないと、漏えい時に責任が曖昧になります。
「受領者は再委託先にも同等の秘密保持義務を課し、その履行について連帯して責任を負う」旨を明記し、重要工程は再委託禁止・事前承諾制とします。
② 成果物に含まれる秘密情報の取扱い
納品物(ソースコード・設計資料等)に秘密情報が含まれる場合、再利用・第三者提示を巡る紛争が起き得ます。
成果物の利用範囲、社外公表の可否、納品後の残存情報の返却・消去を契約で明確化します。
③ SNS・広報活動を通じた情報露出
制作実績紹介のSNS投稿等で、未公開プロジェクトや取引先名が拡散されるケースがあります。
開示可能範囲・社名/ロゴ使用・事前承諾を条項化し、違反時の是正・賠償スキームも定めます。
(3)まとめ:NDAは「信頼関係の補強ツール」
NDAは、あくまで情報漏えいを防止する最低限の法的インフラです。契約書の存在だけでリスクが消えるわけではなく、実運用(アクセス制限、情報区分、ログ管理、教育)が伴って初めて実効性が生まれます。
5 まとめ:NDAのリーガルチェックは「取引を守るための最後の砦」
(1)弁護士によるリーガルチェックが必要な理由
NDAのひな形はネット上に多くありますが、実際の取引実態に即した修正・交渉には法的判断が不可欠です。秘密情報の範囲、再委託・再提供、違反時の調査報告義務、差止・損害賠償・解除権、そして本体契約との整合性まで、弁護士のチェックによって契約全体のリスク像を把握できます。
(2)不適切なNDAがもたらした実際のトラブル事例
筆者が以前に対応した小規模M&A案件では、締結されたNDAに不備があり、情報管理の範囲が曖昧でした。買い手担当者がデューデリジェンスで得た財務情報や経営課題を、何気なく売り手企業の従業員に伝達。社内に動揺が広がり、主要人材が離反、企業価値が低下し、最終的に買収交渉は頓挫しました。
本来は、内部者への再開示禁止/従業員への開示制限/違反時の即時解除権・差止・損害賠償を明記していれば、防げた可能性が高い事案です。
企業売却時に備えた法務・財務の磨き上げ(企業売却・M&Aで高く売るために必要な法務・財務)についても併せてご覧ください。
(3)顧問弁護士による継続的な運用支援
NDAは一度作れば終わりではありません。データルームやクラウド共有、海外事業者との契約、外注・再委託など、取引形態が変われば守るべき情報や責任範囲も変わります。
福岡を拠点とする弁護士法人本江法律事務所では、顧問契約の一環として、NDAの定期的な見直し・契約改訂・運用指導を通じ、企業の法的リスクを継続的に低減します。
(4)契約は「権利を明確化する設計図」
NDAの本質は、単なる情報保護ではなく、企業が守るべき権利と信頼を明確に設計することにあります。重要な取引前には、必ず弁護士によるリーガルチェックを受け、将来の紛争を未然に防ぐ設計を行ってください。
福岡でのNDA・契約書リーガルチェックや顧問弁護士サービスに関するご相談は、弁護士法人本江法律事務所まで。貴社の情報・信頼・事業価値を法的に確実に保護する仕組みづくりをサポートします。
付録:よくある質問(FAQ)
Q1. 投資家がNDAにサインしてくれなくても交渉は進められますか?
A. はい。交渉ステージに応じた段階的な情報開示(一般情報→限定情報)で対応可能です。特に秘匿性の高い技術情報については、投資検討の最終段階での限定開示にとどめましょう。
Q2. 業務委託先が再委託する場合の最低限の条項は?
A. 同等の秘密保持義務を課すことを義務付け(フロー・ダウン)、更に情報漏えい時における連帯責任や、第三者提供の事前承諾取得義務、プラス重要工程の再委託禁止が基本セットです。
Q3. 契約終了後の秘密保持義務はどの程度が目安?
A. 特に期限を設けない条項例も散見されますが、期限を設けるとすれば、技術情報で概ね5年、営業情報で2~3年が一つの目安です(情報の性質に応じて調整)。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。